| 東亜医学協会会員店 |
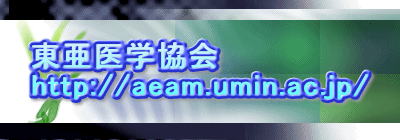 |
|
|
|
陰陽 というのは
病気の時期をさすものさしと考えるとわかりやすいと思います。
東洋医学的な病気の診方は、病気というものが、
生体を侵略する力(病邪)と
生体にそなわった健康を維持しようという力(体力・自然治癒力)との
戦いとみなしています。
病邪に犯された状態でいると 時間の経過とともに
体力は落ちその反対に病邪は勢いを増すということになります。
体力と病邪との優劣で体力>病邪の状態を陽、
体力<病邪の状態を陰といいます。
陽証(ここでの証は状態もしくは時期をいう)では
病邪に対して体力が優位ですから、
戦いは激しく熱を伴うことが多いですが、体力・回復力があるので、
病邪を追い出す薬方を用いることになります。
陰証では 体力が病邪より劣勢となったときですから、
体力・回復力を上げる薬方を用いながら、
病邪を追い出す薬方を用いることになります。
一般的には陰証の病の方が重篤なことが多いです。
陰陽のものさしは 更に三陰三陽という病位に分けます。
〔発病〕→[太陽病] → [少陽病] → [陽明病] →
[太陰病] → [少陰病] → [厥陰病] → [死]の順に進行していきます。
漢方医学では、患者さんの病がどの病位まで進んできているか
判断し治療していきます。
『傷寒論』という漢方の原典の一つに
「病発熱悪寒有る者は、陽発する也。熱無く悪寒する者は陰に発する也。」
(第7章)とあります。
まさに陰陽と病状の関係を表した一文です。
同じ風邪という病名の患者さんでも、薬方は違いますし、
患者さんの風邪の陰陽によっても、薬方は違ってきます。
|
|
|